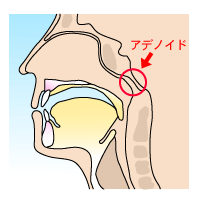いびき・無呼吸症候群の主な原因
いびきとは睡眠時に発生する粘膜の振動音です。主な原因としては肥満、アルコール、薬物、アデノイド、咽頭部の異常、鼻疾患などがあります。
睡眠中に咽頭や舌の筋肉の緊張が低下したときや、アデノイドなどの鼻疾患、咽頭部の障害によって気道が閉塞するときにおこります。いずれも睡眠中は空気の通り道(気道)がふさがれ狭くなり、そこに空気が通ると粘膜が振動しいびきの発生となります。 |
|||||||||||||||||||||
いびきは体重の増加とともにその割合も多くなります。体重が増えるに連れ、顎の周囲、首周り、喉や舌も太くなり、その結果気道が上下左右から圧迫され気道が狭くなりいびきの発生につながります。 対策→減量(ダイエット)
骨格(小さな顎):小さな顎では歯並びが乱れるほかに舌を収めることが出来ません。収まり切れなくなった舌は後方に押し出され気道を圧迫しいびきや無呼吸症候群となります。歯を抜かず顎を広げる歯列矯正なども効果的です。 年齢:年齢による筋力の低下によりいびきを発生することがあります。
体内にアルコールが入ると気道内が充血し粘膜が膨張します。鼻が詰まった感じになるわけです。また舌や咽頭の筋肉の緊張がなくなり気道が狭くなりいびきの発生につながります。対策→禁酒
筋弛緩薬、睡眠薬、精神安定剤などは筋の緊張を緩和させる作用があり、舌や咽頭の筋肉の緊張がなくなり気道が狭くなりいびきの発生につながります。
アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などは鼻の通りが悪くなりがちで、粘膜の抵抗が大きくなりいびきの発生につながります。
咽頭扁桃、口蓋垂(のどちんこ)の炎症や肥大により気道が狭くなり、いびきの発生につながります。 いびきにはこのような原因がありますが、睡眠時に呼吸が止まり無呼吸になっているときには |
|||||||||||||||||||||
Copyright Hirokawa.Dental Clinic All Rights Reserved.
|広川歯科医院|白宝デンタルクリニック|